健康保険に加入する人
本人:被保険者
健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。
また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することになっています。

家族:被扶養者
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
また、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
被扶養者になるための条件
①被扶養者の範囲(三親等内の親族)に含まれていること
②主として被保険者に生計を維持されていること
①被扶養者の範囲
被扶養者となるためには、原則として国内に居住していて、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。
| 被保険者と同居でも別居でもよい人 | 被保険者と同居が条件の人 |
|---|---|
|
|
被扶養者認定における国内居住要件
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
●国内居住要件の考え方
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
●国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- (1)外国において留学をする学生
- (2)外国に赴任する被保険者に同行する者
- (3)観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- (4)被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- (5)(1)から(4)までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
●国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大
1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。
- (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
- (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
- (3)月額賃金が8.8万円以上であること
- (4)学生でないこと
- (5)常時51人以上の従業員を使用する企業に勤めていること
(労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。)
●三親等内の親族とは?
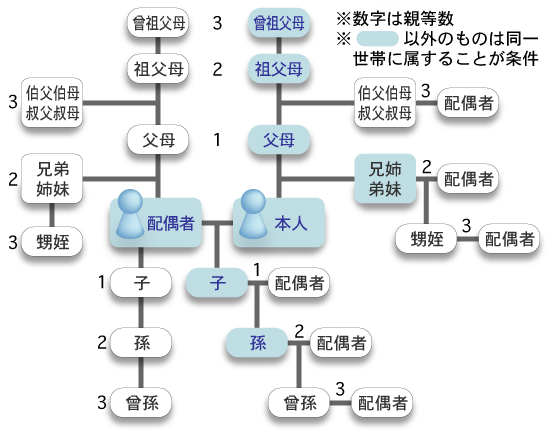
②主として被保険者に生計を維持されていること
※以下の「認定対象者」とは健康保険の被扶養者として申請する家族のことをいいます。
「主として被保険者に生計を維持されていること」とは、一般には認定対象者の生活費の半分以上を被保険者が負担し、現在(または一時的)だけではなく将来にわたって安定的・継続的に維持される状態をいい、認定対象者に収入がある場合は以下の基準により判断します。
ただし、以下の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くことになると認められた場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うことになります。
認定対象者に収入がある場合
- ●被保険者と同居の場合…
- 認定対象者の収入が厚生労働省通達に基づく収入限度額未満で、被保険者の年収の半分未満であること。
- ●被保険者と別居の場合…
- 認定対象者の収入が厚生労働省通達に基づく収入限度額未満で、被保険者からの仕送り額より少ないこと。
| 年齢 | 年間収入 | 月額換算 | 日額換算 | |
|---|---|---|---|---|
| 60歳未満 | 130万円未満 | 108,334円未満 | 3,612円未満 | |
| 19歳以上23歳未満※ (被保険者の配偶者を除く) |
150万円未満 | 125,000円未満 | 4,167円未満 | |
|
60歳以上または 障害厚生年金の受給要件に 該当する程度の障害者 |
180万円未満 | 150,000円未満 | 5,000円未満 | |
- ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定します。(年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日に加算されます。)
日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について
平成30年8月29日、厚生労働省保険局保険課長通知により、
日本国内に住所を有するご家族の方を被扶養者として認定する際は、続柄、同居の事実および生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、公的証明書類等に基づく認定を徹底するよう事務の取り扱いが示されました。
■身分関係(続柄・同居の事実)の確認
厚生労働省から示された取り扱いでは、戸籍謄本(抄本)や住民票の添付によって、被保険者と認定対象者の続柄を確認することとされています。
ただし、次の①②のいずれにも該当している場合は添付書類を省略できることとします。
①被扶養者異動届に被保険者と認定対象者の個人番号が記載されていること
②戸籍謄本(抄本)や住民票等によって、事業主が認定対象者の続柄を確認していること
■生計維持関係の確認
(1)認定対象者の収入の確認
国内認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円未満)であることを公的証明書類等で確認する。
(2)被保険者と国内認定対象者が同一世帯である場合の確認
上記(1)の確認に加え、同一世帯であること公的証明書類等で確認する。
(3)被保険者と国内認定対象者が同一世帯に属していない場合の確認
上記(1)の確認に加え、国内認定対象者に対する被保険者からの送金事実と仕送り額について次の証拠書類で確認する。
①仕送りが振込の場合…預金通帳等の写し
②仕送りが送金の場合…現金書留の控えや写し
※①②いずれも、仕送り人が被保険者であって受取人が認定対象者であることがわかるもの。また、振込(送金)の日付(および回数)と金額から1年間の仕送り額がわかるもの。
※「現金の手渡し」など申立てのみによる申請は認められません。
※被扶養者認定後に実施する「被扶養者状況確認調査」にて仕送り実績の確認をするため、上記証拠書類は必ず提出できるように保管してください。事実が確認できない場合は、被扶養者として認められない場合があります。
※省略できる場合…認定対象者が16歳未満、または学生の場合(一部除く)
添付書類に関しては「」でご確認ください。なお状況によっては一覧表以外の書類を追加でお願いする場合もあります。
もっと詳しく
- 同一世帯とは
-
住居および家計を共にしている状況をいいます。
もう少し具体的にいうと、同じ住居に住んで家庭生活において1つの経済単位を持つことです。
以下の場合は、住所が同じであっても同一世帯とは認められません。
被扶養者の認定申請をする場合は「別居」と申告のうえ「仕送り証明書」を添付してください。- ・同じ屋根の下で暮らしているが、家計が別々の場合(2世帯住宅など)
- ・同じマンションの号室違いで居住している場合
- ・別に居住するところがあり、2箇所以上の家を頻繁に行き来している場合
同居?別居?
被扶養者の認定申請および被扶養者状況確認調査時に、被保険者と同居か別居かを申告していだく欄があります。これは先に説明したとおり、被保険者と住居と家計を共にしているかどうかを確認するために設けた項目です。
被保険者が単身赴任中の場合や被扶養者(認定対象者)が学生で就学のため親元から離れて暮らしている場合などは、家計が同じでも居住は違うので別居になります。
なお、この場合は家計が同じであるため「仕送り証明書」の添付は不要です(一部例外もあります)。 - 年間収入とは
-
被扶養者の認定申請のときに申告していただく収入とは、過去における収入ではなく、申請時点の年間収入見込み額のことをいいます。
年間収入には、給与、年金、事業収入の他に雇用保険の失業給付、健康保険の傷病手当金や出産手当金・他家族からの生活支援金など生活費に充当できるものすべてを含みます。- ※見込み額の算出方法は【収入の範囲】でご確認ください。
- 仕送りの証明
-
被扶養者(認定対象者)が離れて暮らしている場合、被保険者からの仕送り額で生活しているかどうかを公平に判定するために、生活費は原則として毎月送金することが認定条件に含まれます。
数か月分をまとめて送金することや手渡しでは内容を確認することができないため認めていません。
被扶養者の認定申請および被扶養者状況確認調査時、その他に健康保険組合が必要と認めたときは、直近3ヵ月分の仕送り証明書を提出していただきます(場合によっては3ヵ月以上の提出を求めることもあります)。- ※継続した仕送りによる生計維持が確認できない場合は、被扶養者の認定を見直すことがあります。
仕送り証明書とは…
現金書留の送金者控え、銀行振込控え、受取人名義への預け入れを確認できる通帳の写しなど
- ※被保険者が単身赴任で暮らすときや就学のために離れて暮らすときは不要
- ※いったん社会人になった子が離職して再び就学のため離れて暮らす場合は必要
- 収入の範囲
-
被扶養者(認定対象者)の収入とは、原則として次に示すような継続的に生じる収入のすべてをいいます。
収入の種類 内容 算出方法 ①給与収入 勤労所得(給料)・賞与など
労働の対価としての収入通勤交通費等の非課税収入を含む総支給額 ②各種年金収入 厚生年金・国民年金・共済年金・船員農業者年金・石炭鉱業年金・議員年金・労働者災害補償年金・企業年金・各種恩給・自社年金・非課税扱いの遺族年金・障害年金など 介護保険料を控除する前の額
※非課税の年金も収入に含む
③事業収入 農業・漁業・商業・工業など自家営業に基づく所得および保険の外交・芸術家・芸能人・スポーツ選手・医師・各種士業・文筆業など自ら事業を営み得る収入 売上収入から原価と経費(減価償却や青色申告特別控除、引当金繰入金など現金支出がないものを除く)を控除した額
※健康保険組合が認める経費は税法上のものとは異なります。④不動産収入 土地・家屋・駐車場等の賃貸収入 ⑤利子収入 預貯金・有価証券など 利子所得の総額(源泉徴収前) ⑥投資収入 株式の配当・証券投資信託の収益の分配・出資の剰余金の分配など 配当所得=収入金額‐負債利子
(源泉徴収前)⑦雑収入 原稿料・印税・講演料など ③④に同じ ⑧健康保険の傷病手当金・出産手当金 退職後も継続して受ける健康保険の保険給付金 給付日額×360日(年収換算) ⑨雇用保険の失業給付・傷病手当 退職後の生活補償として受け取る給付金 給付日額×360日(年収換算) ⑩被保険者以外からの補助金 生活費・養育費など 補助金総額 ⑪その他 被保険者からの生活費
その他生活費に充当できるもの収入総額 - 夫婦が共働きの場合における子の被扶養者認定
夫婦が共に働いている状態で、それぞれが被保険者として健康保険に加入している場合、子どもの被扶養者認定については、令和3年4月30日 保険発第0430号で以下のとおり通知されています。
- ①被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入(今後の1年間の見込み収入)の多い方の被扶養者とすることを原則とする。
- ②夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
- ③夫婦の双方または一方が共済組合の組合員であって、その者に当該被扶養者に関し、扶養手当またはこれに相当する手当の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。
などです。詳しい内容については、下記をごらんください。
- 両親の被扶養者認定
-
夫婦ともに生活し助け合い、扶助し合う義務があることから、強い生計維持関係があります。従って両親のそれぞれの年収が限度内であっても、双方の年収を合計すれば生計が維持できると判断される場合は被扶養者として認定されない場合もあります。
(参考)
民法752条:夫婦の同居義務と扶養義務
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」
民法760条:婚姻生活費用の共同負担
「夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」 - 16歳以上の家族
-
配偶者と就労経験のない全日制教育機関に就学している者を除く16歳以上の方は、就労可能年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できる場合があります。
被扶養者の認定申請および扶養状況確認調査時には、就労できない理由などとくに扶養しなければならない事情などを正しく申告することが必要です。 - 自営業者の被扶養者認定
-
自営業者(フリーランス等も含む)の方でも、健康保険の被扶養者認定条件に該当していれば被扶養者として加入することができます。
ただし、本来、自営業者が加入する医療保険は国民健康保険になります。
また、事業所得とは、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業、その他事業から生じる所得と定義し、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得という点からみて、事業所得がある場合は、被保険者がとくに扶養しなければいけない状態であることを証明する必要があります。 - 自営業者の収入(事業収入)
-
自営業者の収入はその年の1月1日から12月31日までに生じた総収入金額から必要最小限の経費を差し引いて求めますが、必要経費に家事費は含みません。また、資金の流出がない経費および所得控除は総収入から差し引くことはできません。なお、健康保険組合が認める必要経費とは税法上とは異なります。
【収入から差し引くことができないもの】
- ・青色申告特別控除
- ・減価償却費
- ・貸倒引当金繰入繰戻
- ・家事費
- ・私的に使用された可能性のある経費
- 雇用保険の失業給付について
-
認定申請者が退職したことによる届出の場合は、雇用保険の失業給付に関して受給資格の有無と受給意思の有無を確認するため、「雇用保険の失業給付に係る誓約書」および雇用保険に関する書類の提出をお願いします。
申請事由発生から1ヵ月以内に届出が提出された場合は、事由発生日まで遡り認定しますが、正当な理由がなく遅れた場合は、届出が提出された日が認定日になります。- ※雇用保険に関する書類が揃わない場合は、「雇用保険の失業給付に係る誓約書」にその旨を申し出ることで必要期間の遅延を認めます。ただし、すべての書類が揃うまで資格確認書を交付することはできません。
なお、失業給付を受給する場合は、雇用保険の目的に鑑み、原則としては被扶養者にはなれませんが、以下の認定条件1と2に該当した場合は、申請により被扶養者として認定されます。
《認定条件1》
・失業後、主として被保険者に生計を維持されていることが認められる場合
《認定条件2》(①②どちらかに該当すれば可)
①失業給付の日額が被扶養者になるための収入限度額(日額)を超えていない場合
②自己都合等で退職し、失業給付受給まで1ヵ月から3ヵ月の給付制限期間がある場合
【注意】
- ・会社都合による退職等で給付制限なし(待期期間7日のみ)で、かつ、失業給付の日額が収入限度額(日額)を超えている場合は、被扶養者として認定することはできません。
失業給付受給満了日の翌日以降、被扶養者認定条件に該当すれば申請が可能となります。 - ・自己都合による退職(給付制限期間あり)であっても、特定理由離職者と認められた場合は、給付制限なしに変更されるため、会社都合による退職と同様の取り扱いになります。
- ・給付制限ありの場合でも、失業給付が収入限度額(日額)を超えた場合は、受給開始の日で被扶養者認定条件から外れるため「被扶養者異動(削除申請)届」の提出が必要です。
- ・雇用保険の給付金は失業給付のほか、職業訓練給付金等がありますが、すべて給付・手当金等が収入対象となります。
- ・給付日額が改定され収入限度額(日額)を超えた場合は、改定日で被扶養者認定条件から外れるため「被扶養者異動(削除申請)届」の提出が必要です。
- ・失業給付を受給される場合は、退職後はすみやかにハローワークで手続きを行い「雇用保険受給資格者証」の交付を受けてください。手続きが遅れると被扶養者の認定可否の判断ができず、認定条件に該当していても資格確認書の交付が遅れる原因になります。
◆雇用保険に関する提出書類一覧表◆ 雇用保険(失業給付)に関して 提出書類内容(すべて写し) 雇用保険未加入 未加入を証明する書類または給与明細書 受給資格がない(加入期間不足等) 「雇用保険資格喪失確認通知書」 受給しない(放棄) 「離職票1」「離職票2」に不支給を証明する
ハローワークの「法第4条第3項不該当」の押印があるもの受給延長する 「離職票1」「離職票2」「受給期間延長通知書」 受給申請をする 「離職票1」「離職票2」
申請後に「雇用保険受給資格者証(全頁)」失業給付の待期期間中
または給付制限期間中「雇用保険受給資格者証(全頁)」 受給中 「雇用保険受給資格者証(全頁)」 受給終了 「雇用保険受給資格者証(全頁)」 - 被保険者・被扶養者が75歳になった場合
-
平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。




