退職後の医療保険
退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します(ただし雇用形態によって加入できない場合もあります)。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2ヵ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子どもが被保険者として加入している医療保険に被扶養者として加入することができます。
ただし、被扶養者として加入する条件は各医療保険者によって異なるため事前に確認されることをお勧めします。
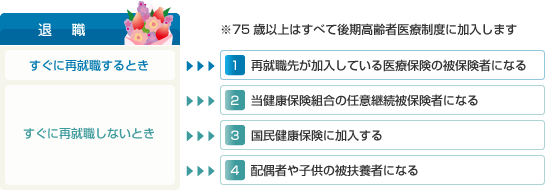
被保険者の資格を失ったときの手続き
- 必要書類
-
- 提出先:
- 各事業所(会社)の人事(業務)担当部署経由で
公文健康保険組合へ提出
- 「資格確認書」(交付されている場合かつ有効期限に達していない場合)
- ※資格を失った日から5日以内に返納してください。
- ※その他に「限度額適用認定証」・「高齢受給者証」・「特定疾病療養受療証」の交付を受けている場合は併せて返納してください。
- ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
「資格喪失証明書」の交付手続き
公文健康保険組合の資格を喪失したあと、次の医療保険への加入手続きを行う際に「資格喪失証明書」の提出を求められることがあります。
- 必要書類
-
- 提出先:
- 各事業所(会社)の人事(業務)担当部署経由で
公文健康保険組合へ提出
- ※退職後に申請する場合は、公文健康保険組合に直接でもかまいません
-
- 「資格喪失証明書交付申請書」
健康保険の資格を失ったあと、公文健康保険組合の加入資格で受診した場合
マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付していますが、資格喪失後、有効期限に達していない「資格確認書」を使って医療機関にかかった場合、その医療費は公文健康保険組合に請求されます。
後日、全額返還していただくことになるため、資格喪失後は速やかに「資格確認書」をご返却ください。
※資格喪失する前に有効期限に達している「資格確認書」は返却不要です。
公文健康保険組合から返還通知が届いたら同封されている「納入通知書兼領収書」を使って期日までに納付してください。
納付時に「領収書」が交付されます。「領収書」は新しく加入した健康保険組合等に「療養費」の請求を行う際に必要です。ATMやネットバンキング等を利用された場合「領収書」は発行されませんのでご注意ください。
【新しく加入した健康保険組合等に療養費として請求するには】
医療費(返還金)の納付時に交付される「領収書」と公文健康保険組合が保管している「診療報酬明細書」を添えて請求手続きを行う必要があります。
- ※「診療報酬明細書」が必要な方はご連絡ください。返還金の納付を確認次第お送りいたします。
- ※請求に必要な申請書やその他詳しい手続きは、請求先の健康保険組合等にお問い合わせください。
資格喪失後に受診した医療費を公文健康保険組合と新しく加入した保険者間で調整できるようになりました。
平成27年1月より被保険者等と公文健康保険組合との間で受領委任等がなされた場合は、保険者間調整が可能となりました。
公文健康保険組合の資格を喪失した後に発生する医療費に関して、保険者間調整を希望される方は下記の書類をご提出ください。
なお、新しく加入した保険者が保険者間調整を取り扱っていない場合や公文健康保険組合が代理申請等することに同意できない場合は、従来どおりの方法で被保険者等が医療費の返還手続きを行うことになります。
- 必要書類
-
- 提出先:
- 公文健康保険組合
もっと詳しく
- 国民健康保険
-
国民健康保険は農業や自営業、自由業など地域住民が加入する医療保険で、都道府県と市区町村が一体となり運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。くわしくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。




